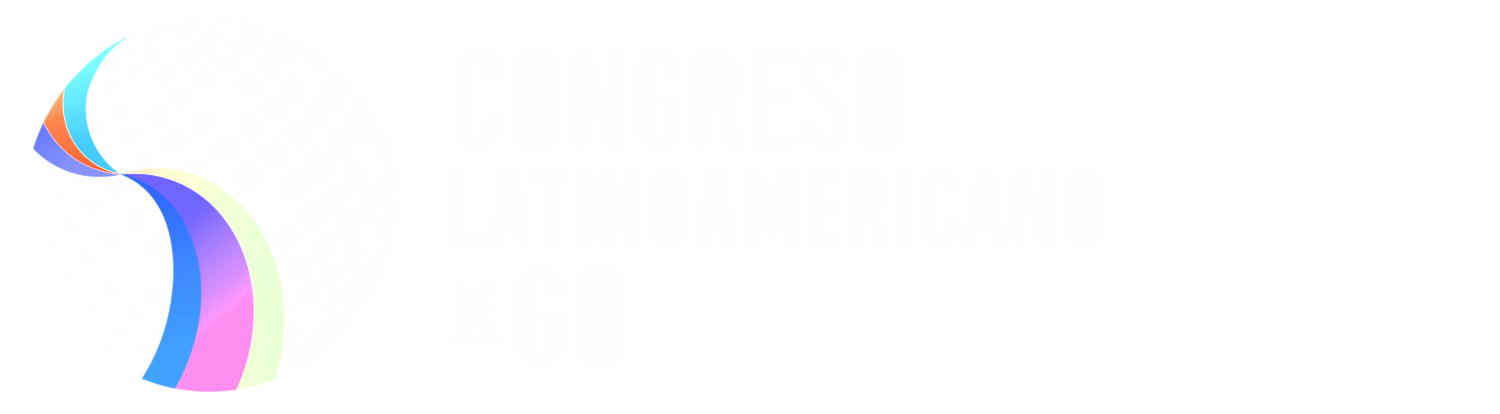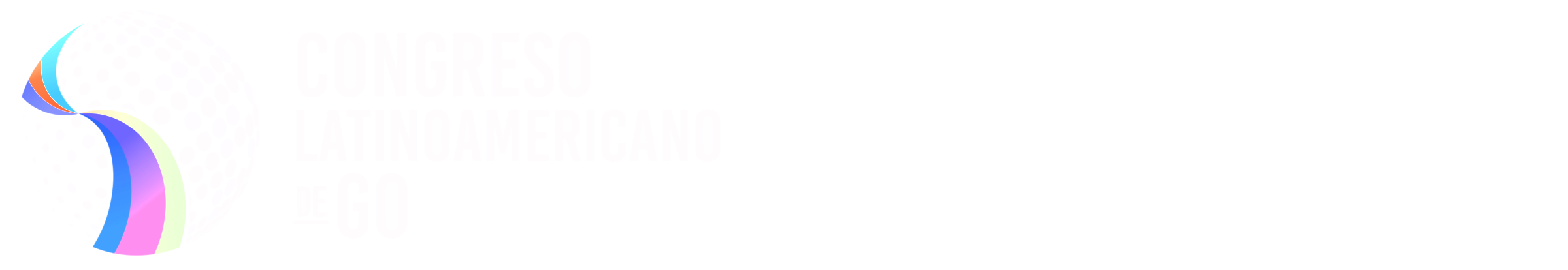イベロアメリカ囲碁連盟
事務局長
ルシアノ・サレルノ
21世紀に碁を覚えた我々が、ハンス・ピーチ六段のことを想うとき、そこには「影」あるいは「謎」がつきまとう。ハンスは碁の世界で、アジア、ヨーロッパ、ラテンアメリカという、まるで異なる3つの舞台に足跡を刻んでいった。そして、それぞれの舞台は彼にとって異なる意味を持っていた。ヨーロッパでは、碁の技術的なレベルがまだ現在とは比べ物にならなかった時代に、棋士として先駆的な存在となった。日本では、20世紀の西洋の碁界に対する日本の大きな貢献の最後の一翼を担った。グアテマラでは、彼の教えることへの意欲と、この南米大陸の嘆くべき社会的状況が思わぬ出来事を招いた。
ハンス・ピーチは1968年、ドイツ連邦共和国ブレーメン市に生まれた。10歳で碁を覚えた彼は、教室で少し離れたところに座っていた同級生と碁を打てるように、座標で着手を伝える装置まで作ったという。16歳になる頃には、真剣に碁に打ち込むようになっていた。その1年後には有段者となり、3年後には5段に昇段した。
小林千寿六段の助力により、ハンスは80年代末に日本棋院の院生として碁を勉強する機会に恵まれた。東京に移り住み、院生リーグに参加し始めた頃、ハンスは22歳になっていた。大半の院生よりもかなり遅いスタートだ。そのハンデを跳ね返すために、彼は碁に没頭した。
「碁の勉強と無関係のことをするなんて論外だ。今は生活のすべてが碁と結びついていないといけない」。ハンス自身も、1994年にこのように語っている。
日本での修行の中で、ハンスは自分の碁の上達とプロになる目的を優先したのは勿論だが、一方で、自分の役割とアジアの棋士の役割は違うことを意識していた。1994年にドイツの囲碁雑誌Deutsche Go Zeitungに掲載されたインタビューの中で、自分が日本で勉強していることがヨーロッパの人々の励みとなり、彼らも日本に行ってみようという気になるかもしれない、と彼は述べている。他のプレイヤーが上達するよう、インスピレーションを与えることも自分の務めだと考えていたのだ。共に院生時代を送ったソーリン・ゲルマン氏によると、ハンスは碁が盛んではない国で普及活動を行うことも自分の役割だ、と話していたという。
日本での修業を開始して7年後の1997年、ハンスはプロの初段になり、2000年には四段に昇段した。
1997年から2003年については、彼のプロとしての活躍を記した英語(またはスペイン語)の資料が少ない。だが、昇段のペースを見る限りは有望な出だしだろう。プロ1年目にして依田紀基九段を破るという歴史的な勝利を収めてから、グアテマラへ旅立つ2003年までの間に、ハンスは10年前から抱いていた目標のいくつかを達成したと言える。
90年代、ドイツ人のプレイヤーにとって、日本で院生になることは、どのような意味を持っていたのか。それは当時西洋ではまだ関心が薄かった碁に、人生のすべてを捧げるということだろうか。西洋にとって、画期的な出来事だったことは間違いない。ハンスはさまざまな意味で2つの世界———囲碁愛好家のクラブと奥深い囲碁の世界———の距離を一気に縮めた。ドイツの愛棋家ステファン・ブディッグ氏は、ハンスについて次のように語っている。「彼は私たちの中で最強のプレイヤーだった。皆の牽引役でもあり、憧れの存在でもあった。そして、私たちの代表として、碁におけるアジアとの橋渡し役を務めた」。
我々ラテンアメリカのアマチュアにとって、ハンスの経歴は夢物語だ。現実離れしている。ここラテンアメリカでは、アマ初段に到達するのは大きな躍進で、3段以上ともなれば大陸全体でも少なく、怪物と称されてもおかしくないほどの実力だ。ハンスの経験は、厳しい現実の中でも碁の上達が叶うことを証明してくれた。
たゆまぬ努力でもって、プロの世界の壁を打ち破るための試練を乗り越えた後で、ハンスは明らかに碁の発展が遅れている地域に戻ってきた。これは私にとって驚きだ。歴史的に碁の盛んなドイツを飛び出し、世界のトップレベルを目指して日本で修業を重ねたハンスは、再び西洋に戻り、ラテンアメリカで碁を教えることになった。そして、我々にとっては夢でしかなかったものを、この手で触れることのできる現実にしてくれた。
長原芳明七段とともにグアテマラに到着するなり、ハンスは我々の地域ではよくある状況に直面した。アンティグア市で企画された講演と研究会には、人がほとんど集まっていなかった。メディアでの宣伝が不十分だったのだ。それでも、2人は用意された時間を目一杯使い、数少ない受講者に碁のルールなどを紹介した。グアテマラの愛棋家カセレス氏が打ち明けてくれたこのエピソードは、我々の大陸とハンスの属する世界との隔たりを物語っている。
グアテマラ滞在三日目、普及活動の合間に一行は火山を見に出かけた。その道中、休憩をしていたときのこと、彼らは強盗に襲われた。ハンスは上半身に銃弾を受け、病院へ運ばれたが、まもなくそこで息を引き取った。その後、彼の亡骸は母国ドイツへ送られたという。この信じられないような知らせに、碁界には衝撃が走った。当時、囲碁関係のサイトに掲載されたハンスへの別れの言葉を読んでも、その驚きの大きさがうかがい知れる。
ハンスが亡くなり15年、碁界は大きな変化を遂げた。現在、欧米にはプロ制度があり、棋士になるために東洋で暮らす必要はなくなった。西洋での技術的なレベルは向上し、普及も進んでいる。碁は徐々にアジアだけのものではなくなってきているようだ。日本は世界的な碁の発展に貢献し続けているが、もはや絶対的な支援国ではなく、かといって他の囲碁大国がその役割を取って代わったわけでもない。いよいよ我々の「半球」がアジアから「独立」する日が近づいているのかもしれない。
冒頭に、ハンスには「影」あるいは「謎」がつきまとうと書いた。「影」の部分は明らかだろう。彼の死は碁の歴史の中で最も衝撃的な出来事の1つだ。そして、それは我々の大陸のどの国が企画してもおかしくないイベントの最中に起こった。
一方、「謎」とは、これら一連の出来事における「謎」を意味する。34歳の棋士が、故郷から遠く離れた場所での普及活動中に襲われ、命を落としたことは、到底理解不可能なことであり、碁の道を志す人の意欲をそぐものだ。ハンスの情熱がもたらしたこと、と割り切ることなどできない。碁への深い愛情と、より多くの人々に碁を覚えてもらいたい、という強い願いが、彼の人生を形作っていたのは間違いないが、命までかけることになるとは、誰も思いもよらなかっただろう。
夢が現実になる。それは二つの世界を衝突させることでもある。社会の厳しい現実が絶えず襲い掛かかる場所で、まるで異なる文化的要素を持つ、思考や抽象概念を主とする活動を普及させることは、この世界をより良くしようという試みだ。たとえハンスの悔やまれる死やそれにまつわる状況は理解しがたいものでも、この前向きな行動には意味を見出すことができる。それだけではない。ハンスの取り組みと、我々テンアメリカ囲碁界の活動との深いつながりも見ることができる。
ハンス没後15年にグアテマラで開催される第2回ラテンアメリカ碁コングレスは、その目標への一歩になると期待されている。再び皆がグアテマラに赴き、悲劇によって中断された活動を再開することは、ハンスに敬意を表する行為であるだけでなく、彼の尽力と歩んだ道が無駄ではなかったことを示す証ともなる。
Hans Pietsch (1968-2003)

Translated to Japanese by Eduardo López Herrero.
Versión original en español. | English translation at the IGF website.
Hans Pietsch vs. Yoda Norimoto (1997), commented by Younggil An.
Interview by Deutsche Go Zeitung (1994), and game records.
Hans Pietsch page on Sensei’s Library, including an account of his last days by Edgardo Cáceres.
Tribute to Hans by the Nihon Ki in, including messages by his parents and acquaintances.